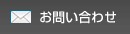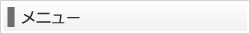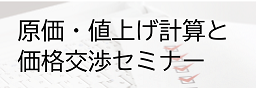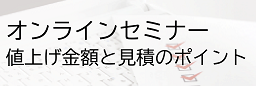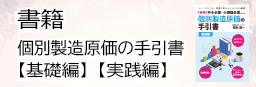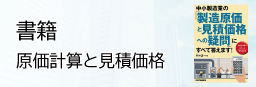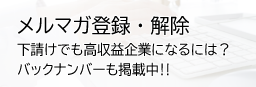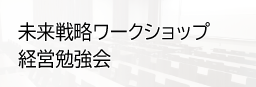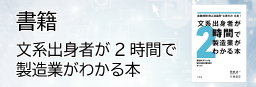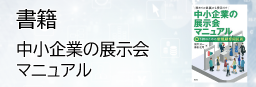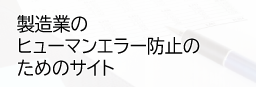コンサルタントの成果とは?
コンサルタントを上手に活用して、会社の業績を高めている場合と、
高額な費用に見合う成果が得られない場合があります。
その違いは何でしょうか?
先日、あるコンサルタントとコンサルタントの成果について議論しました。
人材派遣や外部委託に比べ、
高額なコンサルティング費用に見合う成果とは何なのか?
多くのコンサルタントは、システムソフトや手順書・マニュアルの作成などの
実際の業務をするわけではありません。
以前、経営コラムでコンサルタントの成果とは、「企業を変革すること」と書きました。
コンサルティング計画書は企業変革の設計図
多くの経営上の問題を解決するためには、
組織や管理体制、業務のやり方を変える必要があります。
この企業変革を実現することがコンサルタントの仕事です。
そのためには、問題が解決した将来の姿を具体的にイメージする必要があります。
そして、将来の姿と現状とのギャップを(できれば定量的に)明確にし、
目指す姿へ変革するプロセスを実行しなければなりません。
このプロセスの計画書が、コンサルティング計画書です。

コンサルティングでは、計画だけでなく、その後の実行が必要です。
しかし多くの変革は、クライアント企業の社員の抵抗を伴います。
今までの仕事のやり方、管理体制は、
今までの事業環境に合わせて最適化されたものであり、
合理的な理由があります。
そこを変革しようとすると、大抵は、
「あなたはご存じないかもしれないが…。」
「○○を○○すると、××のような問題が起きるのです。」
このように言われます。
しかし現状の問題は、顧客や技術、競合などの事業環境が変化し、
今までのやり方では対応できなくなったために起きたのです。
これに根本的に解決するには、今のやり方を変えるしかありません。
根本的な部分を変えずに、表面的な対処だけで済まそうとすると、必ず問題が再発します。
仕組みづくりがコンサルティングの成果
このような変化は、クライアント企業内部からは、なかなかできないため、
コンサルタントのような外部の人間が必要とされます。
ただし、そのためにコンサルタント自身が手を下しては、
クライアント企業に仕組みが定着しません。
いくら素晴らしい眼力を持っていて、クライアント企業の気づかない点を次々と指摘しても、
そのコンサルタントがいなくなったら、カイゼンが止まってしまうようでは、企業変革が実現しません。
クライアント企業の方自身が問題点を発見し、解決策を考える仕組みができていないからです。
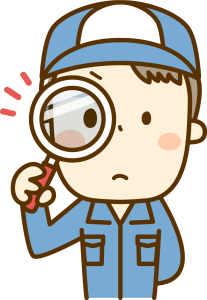
コンサルティングは、クライアント企業の方が自ら問題点を発見し、
改善案を考える仕組みを構築することです。
そしてカイゼンを継続するためには「この仕組みがうまくいっているか」を計測し、
より良くなるように自らが変えていく仕組みが必要です。
このような体制を企業の中に構築することがコンサルタントの成果です。
素晴らしいカイゼンも継続できないと…
工程のレイアウトを自在に変更することで、
生産性を飛躍的に高めた改善に成功した企業がありました。
熱心な管理者と優秀なコンサルタントの先生の指導により、
大きな成果を上げる事ができました。
ところがその熱心な管理者が会社を去った後、
この会社はフレキシブルな生産体制を止め、従来の固定的な配置に戻りました。
この話を聞いたとき、せっかく素晴らしいカイゼンの成果を出しても、
元に戻ったことに驚きました。
つまり成果を出す事がゴールではなく、
変化が持続する仕組みをつくるところがゴールなのです。
なぜなら人は変化を嫌う生き物だからです。
一時的に変化しても、強制的に持続する仕組みができていないと、
時には元に戻ってしまうのです。
コンサルティングに必要なリサーチ
では、どのような仕組みを構築すべきでしょうか?
重要なことは、問題を解決した姿、ゴールのイメージです。
実際には、企業の方がゴールのイメージを持っていない場合があります。
あるいは問題の本質が見えにくい場合、
問題の本質と真の原因を明らかにする必要があります。
そこでコンサルティングに入る前の「リサーチと分析」が必要になります。

経験豊富なコンサルタントは、現場を見ただけで真の原因が分かる場合があります。
ただし、その後クライアント企業の方が仕組みを改善するためには、
クライアント企業の方でも課題が見えるようにする必要があります。
そのためのツールが、データ分析やフレームワークです。
特にデータの分析は重要です。
例えば、在庫が多すぎて問題がある場合、
一定期間の在庫の消費と補充のデータを分析すれば、
どこまで在庫を減らせば良いか、一目瞭然です。
そしてこのような分析手法を定着させることで、継続的な改善が実現します。
コンサルタントは、アドバイス業ではない
「コンサルティング受注の為のリサーチに時間をかけ原因まで分かると、
顧客は分析結果だけもらって自分でやってしまい、受注できないのではないか」
という意見もあります。
しかし仕組みを構築し企業を変革することがコンサルティングであり、
アドバイスはコンサルティングの根幹ではありません。
多くの経営課題は
「分かっていてもできないこと」であり、
「わかっていてもできないこと」をできるようにすることが、
コンサルティングのノウハウです。
従って弊社では、求められればアドバイスはどんどん行っています。
コンサルティングが期間限定のアドバイスや指導であれば、
コンサルティング費用は高いと感じるかもしれません。
しかし課題を解決できるように企業が変革し、
その結果、売上が上がる、利益が増えるという変化が起きる、
そしてその変化が持続するのであれば、
コンサルティング費用は高くないのではないでしょうか?

コンサルタントの効果的な活用方法についての記事は、こちらから参照いただけます。
経営コラム ものづくりの未来と経営
人工知能、フィンテック、5G、技術の進歩は加速しています。また先進国の少子高齢化、格差の拡大と資源争奪など、私たちを取り巻く社会も変化しています。そのような中
ものづくりはどのように変わっていくのでしょうか?
未来の組織や経営は何が求められるのでしょうか?
経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、こういった課題に対するヒントになるコラムです。
こちらにご登録いただきますと、更新情報のメルマガをお送りします。
(登録いただいたメールアドレスは、メルマガ以外には使用しませんので、ご安心ください。)
経営コラムのバックナンバーはこちらをご参照ください。
中小企業でもできる簡単な原価計算のやり方
製造原価、アワーレートを決算書から計算する独自の手法です。中小企業も簡単に個々の製品の原価が計算できます。以下の書籍、セミナーで紹介しています。
書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」
中小企業の現場の実務に沿ったわかりやすい個別製品の原価の手引書です。
基本的な計算方法を解説した【基礎編】と、自動化、外段取化の原価や見えない損失の計算など現場の課題を原価で解説した【実践編】があります。
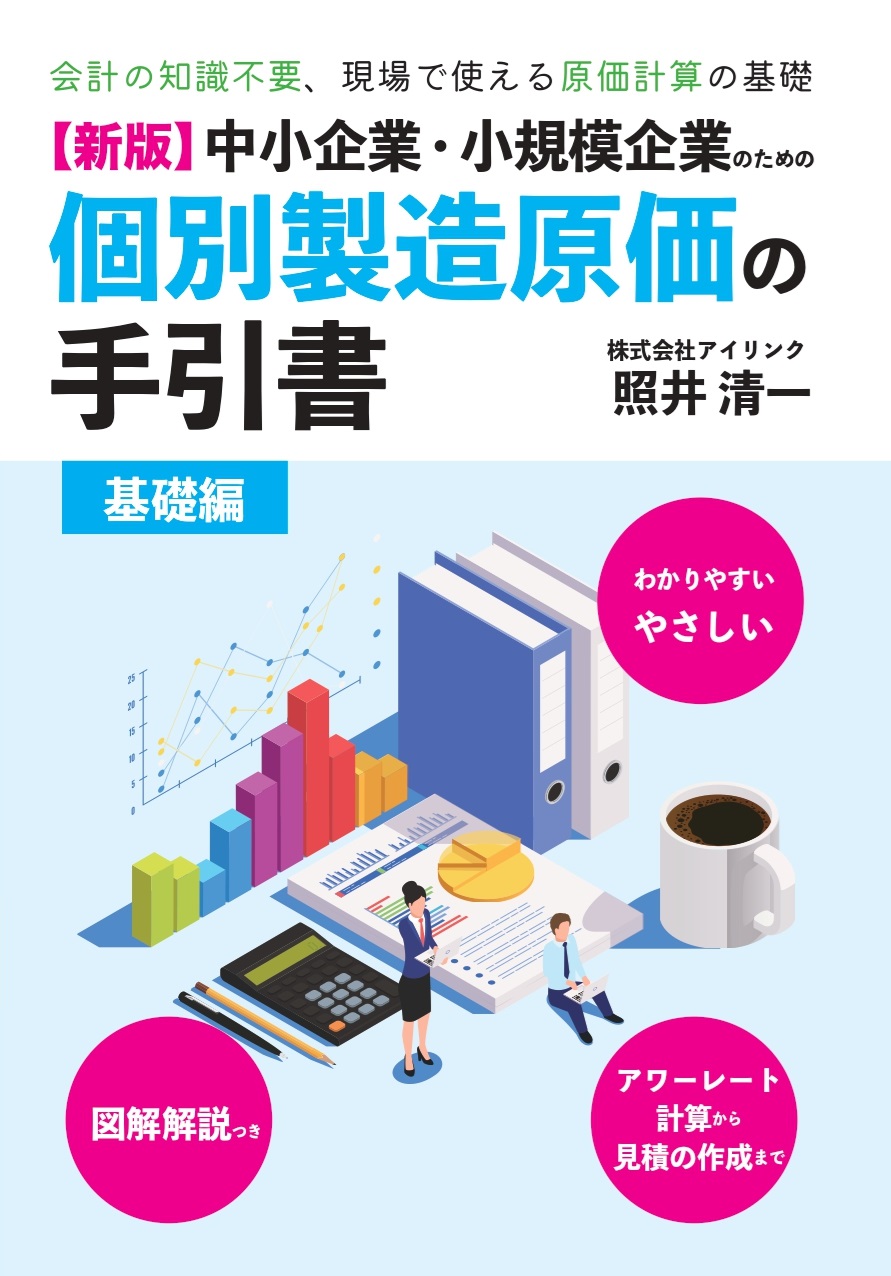
中小企業・小規模企業のための
個別製造原価の手引書 【基礎編】
価格 ¥2,000 + 消費税(¥200)+送料
中小企業・小規模企業のための
個別製造原価の手引書 【実践編】
価格 ¥3,000 + 消費税(¥300)+送料
ご購入及び詳細はこちらをご参照願います。
書籍「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」日刊工業新聞社
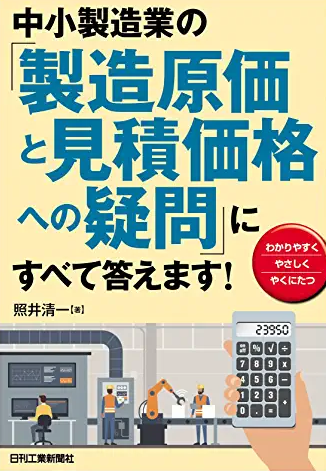
普段疑問に思っている間接費・販管費やアワーレートなど原価と見積について、分かりやすく書きました。会計の知識がなくてもすらすら読める本です。原価管理や経理の方にもお勧めします。
こちら(アマゾン)から購入できます。
簡単、低価格の原価計算システム
数人の会社から使える個別原価計算システム「利益まっくす」
「この製品は、本当はいくらでできているだろうか?」
多くの経営者の疑問です。「利益まっくす」は中小企業が簡単に個別原価を計算できるて価格のシステムです。
設備・現場のアワーレートの違いが容易に計算できます。
間接部門や工場の間接費用も適切に分配されます。
クラウド型でインストール不要、1ライセンスで複数のPCで使えます。
利益まっくすは長年製造業をコンサルティングしてきた当社が製造業の収益改善のために開発したシステムです。
ご関心のある方はこちらからお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。