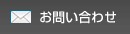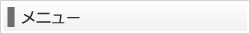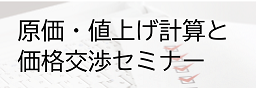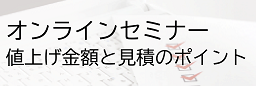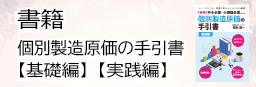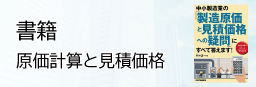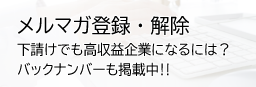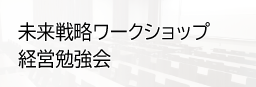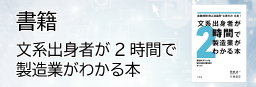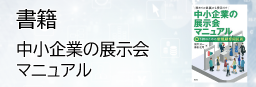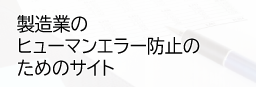製造業で高く受注するためには? サービス業での取組のヒント
製造業の受注活動は、顧客の図面や仕様書から見積りを作成・提出して、受注につなげます。
以前のように多くの企業が好調で発注先を求めていた時代はこれで受注できました。
しかし今では、顧客が価格を設定する指値方式が多くなっています。
しかもその指値は、とても利益が出ないような厳しい価格です。
その上で少しでも安く発注しようと価格交渉を行ってきます。
一方利益確保のためには、少しでも高く受注したいところです。
では、どのようにすれば良いでしょうか。
そのヒントとして、以下のサービス業の取組があります。
先日、中小企業診断士 東條裕一氏の講演を聞きました。
東條氏は、サービス業において、「再現性」と「創造性」をもたらす科学的な方法について講演しました。
サービス業では、顧客に買ってもらうために、店員は様々な方法で顧客にお勧めします。
しかし今では、店員の言葉に顧客は容易には反応してはくれません。
東條氏の考えは、
- 顧客に行動してもらうためには、そういう気持ちになることが必要
- そういう気持ちになるためには、店員は何をしなければならないか考える
- 店員がしなければならないことをマニュアル化し、全員が行う
というものです。
つまり、
- 顧客の行動を最初に設計し、
- その時の顧客の感情を想定して、
- その感情になるように
- 店員の行動を設計します。
顧客の感情が、こちらが意図したように変化すれば、こちらの望む行動、つまり望む結果が得られます。
顧客の感情は、コントロールできませんが、顧客の感情に影響を与える自社の店員の行動は、コントロールできます。
そこで、望む結果が得られるように店員の行動を設計するわけです。
これを顧客が来店してから、成約までの段階で細かく設計します。
例えば、貸衣装店の場合、
1) 予約の電話入れる
2) 来店目的を伝える
3) 来店のきっかけを伝える
4) 来店日時を伝える
5) 来店する
6) 案内された席に着く
中略
17) 試着を楽しむ
18) 契約する
このように18の段階に分解します。
そしてそれぞれの場面で、顧客が思ってほしいことと、そのために行うことを挙げます。
例えば、「衣装の試着を希望する」場合
来店しても、試着するまでには、越えなければならない感情のハードルがあります。
そのハードルを乗り越えて、顧客が試着しようと思うには、顧客はどのような感情になる必要があるでしょうか。
例
【行動】 試着をする
- 顧客の不安 「種類が少なかったらどうしよう」
- 望ましい顧客の感情 「たくさんの衣装から選べそうだな」
- 店員の行動 選択肢が大手と比べて劣らないと思ってもらう。
【具体的な方法】
●トーク1
大型の衣裳店も動いているドレスは、一部です。自社は比較的動くドレスを厳選して取り揃えています。
●トーク2
店内でお気に入りが見つからない時はメーカーから取り寄せもできるのでご安心ください。
このトークをマニュアルにします。
この方法が素晴らしいのは、トークも含めた店員の行動がマニュアル化できる点です。
このマニュアル化の利点は、改善できる点です。
マニュアルに書かれているから、やってみて顧客の反応が違っていたらトークを修正し、それを他の店員に展開できます。
これにより全員がレベルアップし、しかも店員によるバラツキがなくなります。
売れる店員、売れない店員の差がなくなります。
また従来は、おもてなしを重視し、顧客の要望をできる限り聞くようにしていました。
その結果、顧客の要求に振り回され、手間をかけても成約につながらない場合が多くありました。
この方法では、全ての行動が成約という目的に向かっています。
そのため、効果的に店員が行動できます。
ただし、マニュアル化すると画一化された行動になってしまい融通が利かなくなる恐れもあります。
そこでマニュアルの通りに行わなくても良いという規定が入れてあります。
つまり目的を達成する為ならば、他の方法を取っても良いとすることで、店員の自発的な創造性を尊重しています。
実は顧客にとって欲しい行動から考えて、顧客の感情を変える営業トークは
売れる営業が経験的に行っていることです。
売れない営業は、なんとかして商品を売ろうと顧客に「お勧め」します。
これは自分の為です。
「自分の為に買ってください」という営業トークは、顧客の感情を変えることはできません。
売れる営業は、顧客の考えを読み取り、顧客の不安を取り除くことに時間をかけます。
そして、顧客の為であれば、あえて安いものを勧めることもあります。
その結果、顧客は店員を深く信頼し、その結果、売れます。
今回の方法は、この売れる営業のプロセスをマニュアル化し、誰でもできるようにした方法と言えます。
この方法は、製造業の営業でも活用できます。
例えば、図面をもらって見積りを出して受注する場合は、顧客にとって欲しい行動は以下の段階が考えられます。
- 図面を渡す。
- 発注条件を確認する。
- 見積りを受け取る。
- 発注する。
この時の顧客の感情は、
- この会社にも発注するかもしれない。
- 発注条件をしっかり見ているから安心できる
- この価格は適正な価格だ。
- ここに発注すれば安心だ
このような感情を引き出すために行うことは
- それまでに何回か会って、気心が知れている
- もらった図面から、およその納期を推測し、急ぎかどうか確認する。納品場所など他の条件も聞く。
- どうしてこの価格になるのか、わかりやすく説明する。品質を確保するために手間をかけているところを伝える。
- 当社に発注すれば、良い品質、適正なコスト、納期を守ることを理解してもらう。
特に手間のかかる部品や案件は、発注側が価格の根拠を分からないために、一方的に「高い!」「もっと安くして!」という交渉になりがちです。
しかし安くするために、必要な工程を省いたり、質の悪い外注に出せば、品質問題を起こしたり、納期に遅れたりして、結果的に顧客に迷惑がかかり、顧客の費用も増えてしまいます。
よく社長さんが
「うちは手間をかけて良いものを作っているから、品質に自信がある」
と言われます。
この「手間をかけて良いものを作っている」を顧客に伝わるように、
内容を具体的に展開し、営業トークに組み込むと良いのではないでしょうか。
そして自社に発注することで、顧客にメリットがあると思ってもらうのです。
クロード・ホプキンスというアメリカの伝説的なマーケテイングコンサルタントは、アメリカで16位のシュリッツビールをわすが数年で業界首位にまで引き上げました。
彼がシュリッツビール訪れた時、シュリッツビールの人たちは、彼に
水は、五大湖の奥深くからくみ上げた水を使い、
ビンは高温の蒸気で繰り返し洗浄し、
工場内は清潔で、
特別な酵母を使いこだわりを持って作られている
ことを説明しました。
クロード・ホプキンスは言いました。
「なぜこの事をお客様にお伝えしないのですか?」
20年ほど前、私は上司からある板金加工会社を紹介され、その会社を見学しました。
NCタレパンという機械が高速で鉄板を打抜く姿を見せてくれました。
社長は、この機械は精度が高く、低コストで製造できることを強調しました。
後で他の会社に聞きましたが、NCタレパンは多くの板金工場に既に導入され、特別なものではありませんでした。
当時設計をしていた私は、
それぐらい受注側のものづくりを知らなかったのです。
以上、東條氏の顧客の行動を引き出す方法と、
それを製造業の営業に展開する方法をご紹介しました。
ただし、ここで疑問に思った方もいるかもしれません。
「発注側は、常にコストダウンを求めているのに他より高い価格で受注できるわけがない。」
私の経験では、安くても品質に不安があったため、相見積りでも高いところに発注したこともありました。
つまり、顧客を望む行動に導くプロセスに加えて、
競合の情報を収集し、いくらで受注できるのか、計画的に行動する
必要があります。
これについては、別の機会にお知らせします。
経営コラム ものづくりの未来と経営
人工知能、フィンテック、5G、技術の進歩は加速しています。また先進国の少子高齢化、格差の拡大と資源争奪など、私たちを取り巻く社会も変化しています。そのような中
ものづくりはどのように変わっていくのでしょうか?
未来の組織や経営は何が求められるのでしょうか?
経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、こういった課題に対するヒントになるコラムです。
こちらにご登録いただきますと、更新情報のメルマガをお送りします。
(登録いただいたメールアドレスは、メルマガ以外には使用しませんので、ご安心ください。)
経営コラムのバックナンバーはこちらをご参照ください。
中小企業でもできる簡単な原価計算のやり方
製造原価、アワーレートを決算書から計算する独自の手法です。中小企業も簡単に個々の製品の原価が計算できます。以下の書籍、セミナーで紹介しています。
書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」
中小企業の現場の実務に沿ったわかりやすい個別製品の原価の手引書です。
基本的な計算方法を解説した【基礎編】と、自動化、外段取化の原価や見えない損失の計算など現場の課題を原価で解説した【実践編】があります。
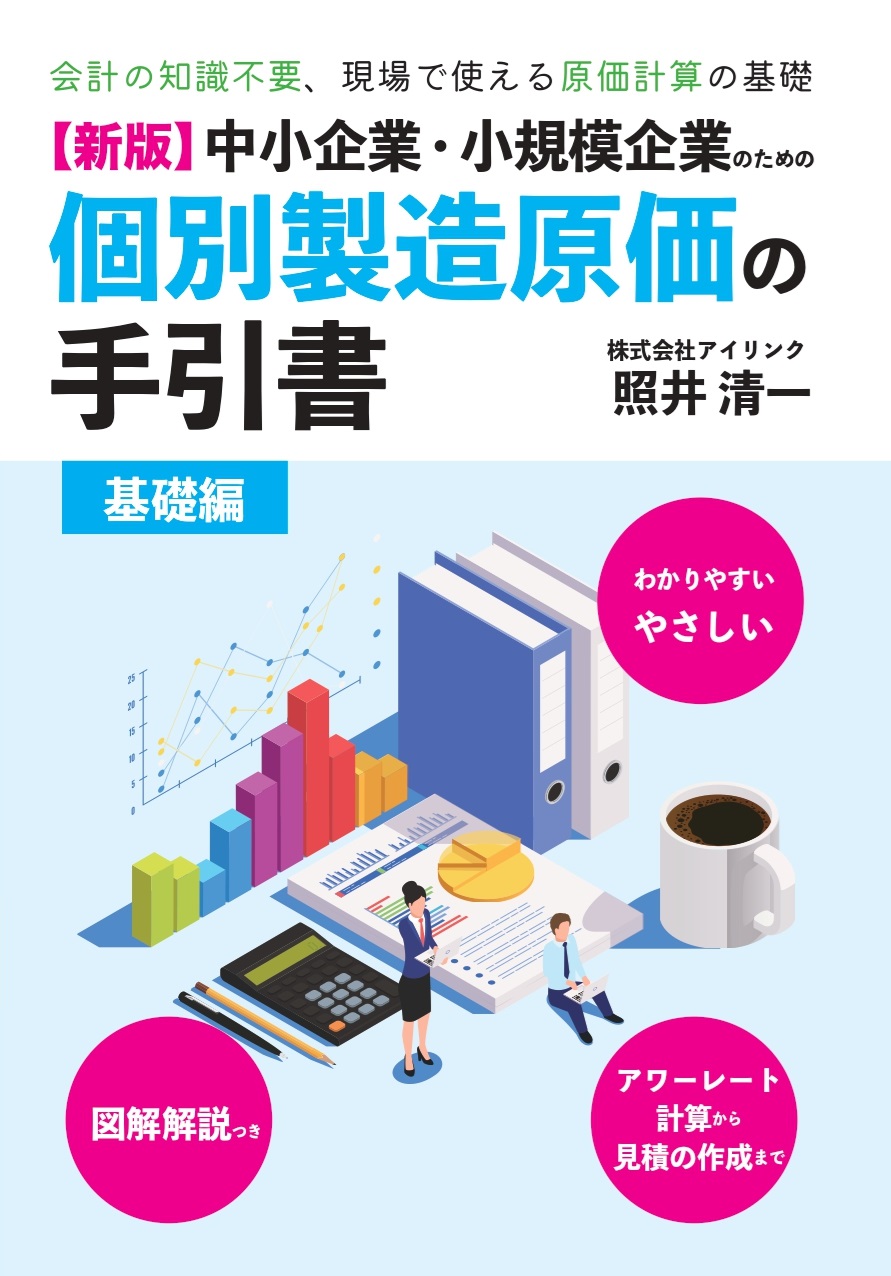
中小企業・小規模企業のための
個別製造原価の手引書 【基礎編】
価格 ¥2,000 + 消費税(¥200)+送料
中小企業・小規模企業のための
個別製造原価の手引書 【実践編】
価格 ¥3,000 + 消費税(¥300)+送料
ご購入及び詳細はこちらをご参照願います。
書籍「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」日刊工業新聞社
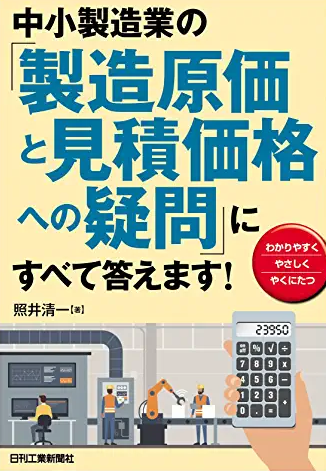
普段疑問に思っている間接費・販管費やアワーレートなど原価と見積について、分かりやすく書きました。会計の知識がなくてもすらすら読める本です。原価管理や経理の方にもお勧めします。
こちら(アマゾン)から購入できます。
簡単、低価格の原価計算システム
数人の会社から使える個別原価計算システム「利益まっくす」
「この製品は、本当はいくらでできているだろうか?」
多くの経営者の疑問です。「利益まっくす」は中小企業が簡単に個別原価を計算できるて価格のシステムです。
設備・現場のアワーレートの違いが容易に計算できます。
間接部門や工場の間接費用も適切に分配されます。
クラウド型でインストール不要、1ライセンスで複数のPCで使えます。
利益まっくすは長年製造業をコンサルティングしてきた当社が製造業の収益改善のために開発したシステムです。
ご関心のある方はこちらからお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。