廃番の自動車ゴム部品を製造する下請け企業は、少量生産と高価格で成功しています。その理由は、部品が車の価値を高め、顧客は適正価格なら購入するからです。BtoBでも、顧客に新たな価値を提供する際は、原価に囚われず、顧客が得るメリットを考慮した価格設定と説明が重要です。
先日、あるゴム部品の下請け企業を訪問しました。同社は、本業の下請けの受注以外に、自動車のレストア部品の製造も行っていました。
自動車のゴム部品は、時間が経つと劣化してゴムとしての性能は大きく低下します。自動車は、サスペンションやエンジンマウントにゴム部品が使われていますが、劣化したゴム部品は新しいものに変えなければ本来の性能は出なくなります。エンジンマウントは劣化して割れてしまえばエンジンを支える事すら出来なくなります。
ところがゴム部品を製造するためは、型にゴムを流し込んで成形しなければなりません。古い車の場合、メーカーは型を処分してしまい部品を供給する事ができません。
そこで同社は自社で型を作り、少量生産に適した機械でゴム部品を成形しています。
現行の自動車は、ゴム部品の原価はせいぜい1個数十円です。しかし部品1個をディーラーから買えば、その何十倍にもなりますが…。
新たに作れば、数十円が数万円に
しかし新たに型を作れば、型の費用がかかるため1個数万円します。ゴム部品をつくる会社からみれば、「そんな高いゴム製品を顧客は買ってくれるのだろうか」、「そんなに高く売っていいのだろうか」という気持ちになります。
しかしこの場合、高くても問題はないのです。古い車に乗っている人は、そのゴム部品がなければ車は動きません。そして古い車が好きな人は、いくら性能が良くても新しい車では満足しません。つまり、他に代わる車はないのです。
ですから、コンディションの良い古い車は、新車より高い価値があります。例えば、初代のフェアレディZやトヨタ2000GTは程度の良いものは、とても高価です。

高価な車がきちんと動くのであれば、ゴム部品が10万円でもオーナーは買います。その部品もいつなくなるかわからないからと、余分に買うかもしれません。
部品だけでなく、車の価値まで部品に含まれる
そのゴム部品の持つ価値は、部品単体の価値だけでなく、古い車が調子よく動くことです。そうであれば、価値はとても高くなります。そして高い価格決定のためには、
「価格=製造原価+利益」
という発想から離れ、製品が生み出す顧客の価値の視点が必要です。
顧客が価格に納得できるストーリー
ただし、販売する際には、その価格のもっともらしい理由が必要です。顧客は「価格=製造原価+利益」と考えるからです。だからと言って、偽りの原価を言う必要はありません。その部品がどれだけ手間がかかって、素晴らしいものかを伝えれば良いのです。
ドモホルンリンクルで有名な再春館製薬所は、自社の製品を作るのにどれだけ手間がかかっているのか、また良い製品をつくるためにどれだけ努力しているのか、具体的な取組を繰り返しテレビCMや広告で訴えています。実際、妻に聞くとドモホルンリンクルは基礎化粧品の中で高いそうです。かといって、どれだけ製造原価がかかっているかは広告からは分かりません。
訴えるべきは顧客のメリット
同様にレストア部品も、訴えるべき内容は、どのような品質で、顧客にどのようなメリットをもたらすかが重要です。例えば、その部品のゴムの配合は、オリジナルの部品と同じであり、同じ特性を持っているなどです。その結果、オリジナルと同等の振動、乗り心地が味わえる、といった特徴を伝えれば、高い価格決定でも納得してくれます。
利益は何のため?
では、たくさん儲けて良いのでしょうか?
今まで下請けとして厳しい価格で受注してきた企業には、B to Cで原価の何倍もの価格決定を行うことにためらう方もいます。しかし、自社の製品として売るためには、そのぐらいの利幅を取らないと事業として継続できません。自ら売る場合は、広告などの販促費用が必要です。小売店や卸に売ってもらう場合は、マージンを払わなくてはなりません。
そして、顧客が自社の製品を良いと思っている場合、利益を上げて事業を継続することを顧客も望んでいます。例えば、ゴムのレストア部品であれば、エンジンマウントを作れば、他のゴム部品も欲しいと思うでしょうし、仲間がいれば他の車の部品も作って欲しいと思うでしょう。そうやって事業を発展させるためには、ある程度の利益が必要です。つまり利益をしっかりとることは、最終的には顧客のためでもあります。
B to Bの場合
では、B to Bの部品ではどうでしょうか?
B to Bでは、顧客は部品の価値が分かっています。従って、ドモホルンリンクルのように如何に手間がかかっているかを訴えても、「それが何?」と言われてしまいます。
では、価値を訴えることはできなのでしょうか?
新たな価値を生み出した時とは?
実は、新たな価値を生み出した時は、価値を訴えることは効果があります。例えば、部品Aと部品Bを一体化して、同等の機能が得られた時、そのような提案を自ら顧客に行い採用された場合、どのような価格決定を行いますか?
2個の部品が1個になったわけですから、顧客にとっても大幅なコスト削減になります。他にも組立の手間がかからない、強度が上がった、軽くなるなどの多くのメリットがあったりします。
しかし「価格=製造原価+利益」で価格決定すれば、得られる利益は限られます。顧客に対し十分なメリットがあれば、もっと価格を上げることができます。ただし、その場合、価格が高い合理的な理由を顧客に説明しなければなりません。このような作り方をするから、これだけの価格になるという論理的な説明です。
価格が1/3になった経験
かつて、13個の薄いゴム部品と金属のプレートを組合せる部品を設計しましたことがあります。別々に部品を作り、組立てる構造にするととても高価な部品になりました。これを一体で作れないか、部品メーカーと打合せし、一体にする方法が見つかりました。ゴムと金属を接合するために、特殊な表面処理を探しました。その結果、部品コストは1/3になりました。それでも部品メーカーには、十分な利益があったようです。
でも、今考えれば、元々の設計の1/3の価格になったのです。この部品メーカーが考えるべきだったことは、もっと高く見積することでした。それでも喜んで発注したでしょう。
部品メーカーは、この一体構造ができなければ、どのような方法を取らざるを得ないか、その時のコストはいくらかを考えて価格決定すべきだったのです。そうすれば、受注した価格の1.5倍をつけることができたでしょうし、それでも私は発注したと思います。
つまりB to Bの取引でも、顧客に新たな価値を生み出した時は、利益の高い受注が可能なのです。しかし、そのためには
「顧客にどれだけの価値を提供できたのか」
を考え、その価格を納得してもらうためのストーリーを作る必要があります。
顧客に提案するためには
そして「価格=製造原価+利益」でなく、顧客の価値の視点で考えるように考え方を変える必要があります。そのためには、常に自社の製品や部品が顧客の製品の中でどのように使われ、より良い製品を作るためには、何か改善できる点はないか考える必要があります。
そのような取組をしている企業は、きっと顧客から欠かせない会社になるのではないでしょうか。
経営コラム ものづくりの未来と経営
経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。
以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)
弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」
原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。
「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」
製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。
書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】
経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。
【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本
【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説
セミナー
アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。
オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。
詳細・お申し込みはこちらから
月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。
利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。

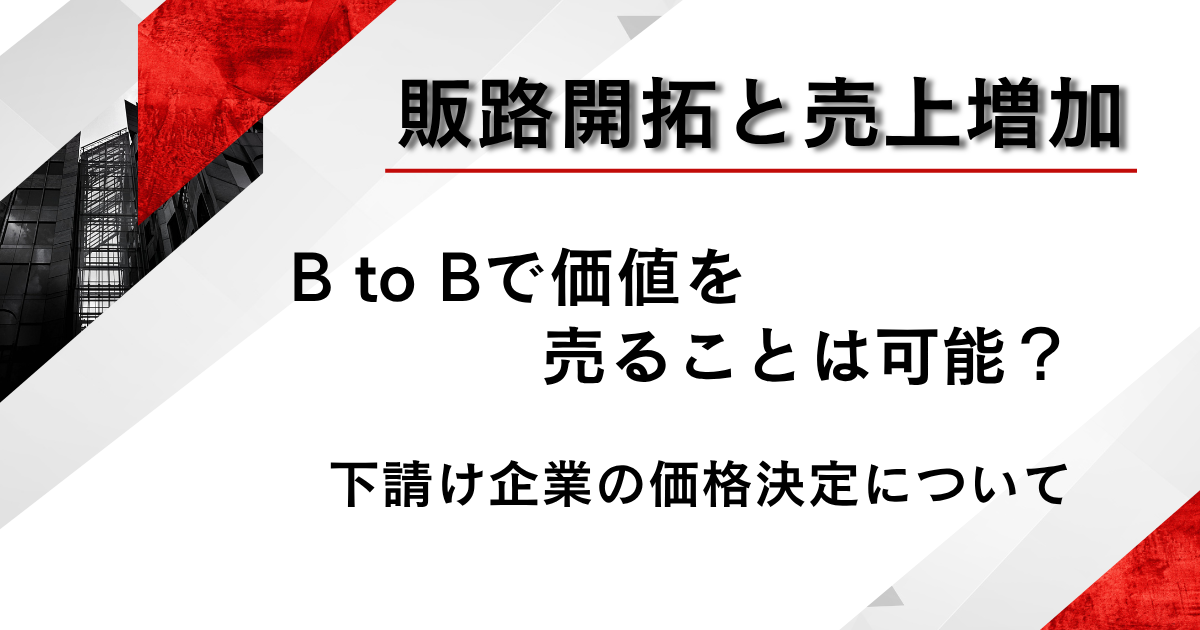

コメント