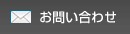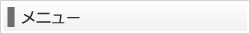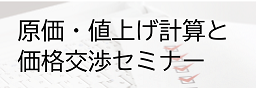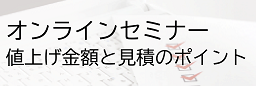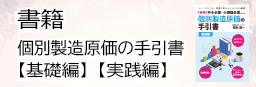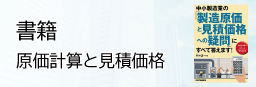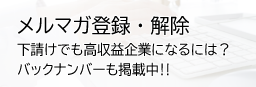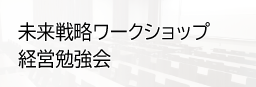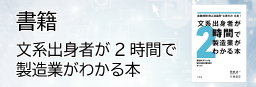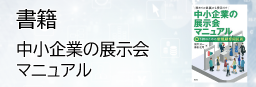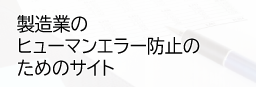中小企業のものづくり改善 ~5Sについて その3
前回は、【整頓】について、「3定」と「ルールを守ること」について述べました。
3定のうちで、〈定量〉と、「置き場所のランク」について述べます。
3定のうち、〈定位〉と〈定品〉が実現できたら、各々の置き場所に最低数量と最大数量を記入し、
〈定量〉を目指します。
その結果、多すぎたり少なすぎたりすれば、一目で分かるようになります。
これは仕掛品が多すぎたり、生産や出荷の遅れなどの異常が、置き場所の最大数量を超えていることで、容易に分かるようになります。
ただし、このような見える化は、現場の管理者や作業者は嫌がり、理由をつけて反対することがあります。
その場合は、管理者が現場のメンバーと良く話し合って、異常がわかることは改善することが目的で有り、決して担当者を責めるわけではないことを納得してもらいます。
また、この〈定量〉も急な受注や欠品で現場が混乱すると守られなくなることがあります。
その場合は、混乱が収束した後は、再度〈定量〉を守るように管理者が指導します。
もうひとつは、「置き場所のランク」です。
実は工場のフロアーは同じようでも、主に物流のアクセスのしやすさから使いやすい場所と、使いにくい場所があります。
例えば、これを一等地から三等地に分類します。
すると
通路に面した場所は、物流がしやすく輸送効率が高いため一等地です。
通路から離れていたり、壁際など片側からしかアクセスできない場所は、二等地です。
さらに奥まっていたり、周りを囲まれていてリフトがアクセスできない場所は、三等地です。
【整頓】して置き場所を決める際も、品物の運びやすさや物流の頻度を考慮して、頻繁に出し入れするものは、一等地に配置します。
実際の中小企業の現場では、一生懸命整理・整頓して空けた場所は三等地で、実は一等地にここ数年使用していない保管品が占拠している、なんて場合があります。
その結果、毎回リフトが保管品をよけながら、ジグザグに運転したいたり、保管品のため台車が通れなくて、大回りしていることになったりします。
しかも多くの作業者は不便だと思っていても、保管品をどけてください、捨ててください、とは滅多に言いません。
その結果、物流に余分な時間がかかり知らぬ間に生産性が低下しています。
こういった点は、現場管理者がよく見て問題に気づく必要があります。
このように有効に使用できる場所を優先的に空け、物量効率を高めることが生産の効率化には必要ですが、
これは意外と気が付かないポイントでもあります。
次回は、清掃、清潔について述べます。
モノづくり改善 ~中小企業の5Sについて その4はこちらからご覧ください。
ものづくり改善 段取り時間短縮については、こちらから参照いただけます。
ものづくり改善 リードタイム短縮については、こちらから参照いただけます。
ものづくり改善 品質改善については、こちらから参照いただけます。
経営コラム ものづくりの未来と経営
人工知能、フィンテック、5G、技術の進歩は加速しています。また先進国の少子高齢化、格差の拡大と資源争奪など、私たちを取り巻く社会も変化しています。そのような中
ものづくりはどのように変わっていくのでしょうか?
未来の組織や経営は何が求められるのでしょうか?
経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、こういった課題に対するヒントになるコラムです。
こちらにご登録いただきますと、更新情報のメルマガをお送りします。
(登録いただいたメールアドレスは、メルマガ以外には使用しませんので、ご安心ください。)
経営コラムのバックナンバーはこちらをご参照ください。
中小企業でもできる簡単な原価計算のやり方
製造原価、アワーレートを決算書から計算する独自の手法です。中小企業も簡単に個々の製品の原価が計算できます。以下の書籍、セミナーで紹介しています。
書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」
中小企業の現場の実務に沿ったわかりやすい個別製品の原価の手引書です。
基本的な計算方法を解説した【基礎編】と、自動化、外段取化の原価や見えない損失の計算など現場の課題を原価で解説した【実践編】があります。
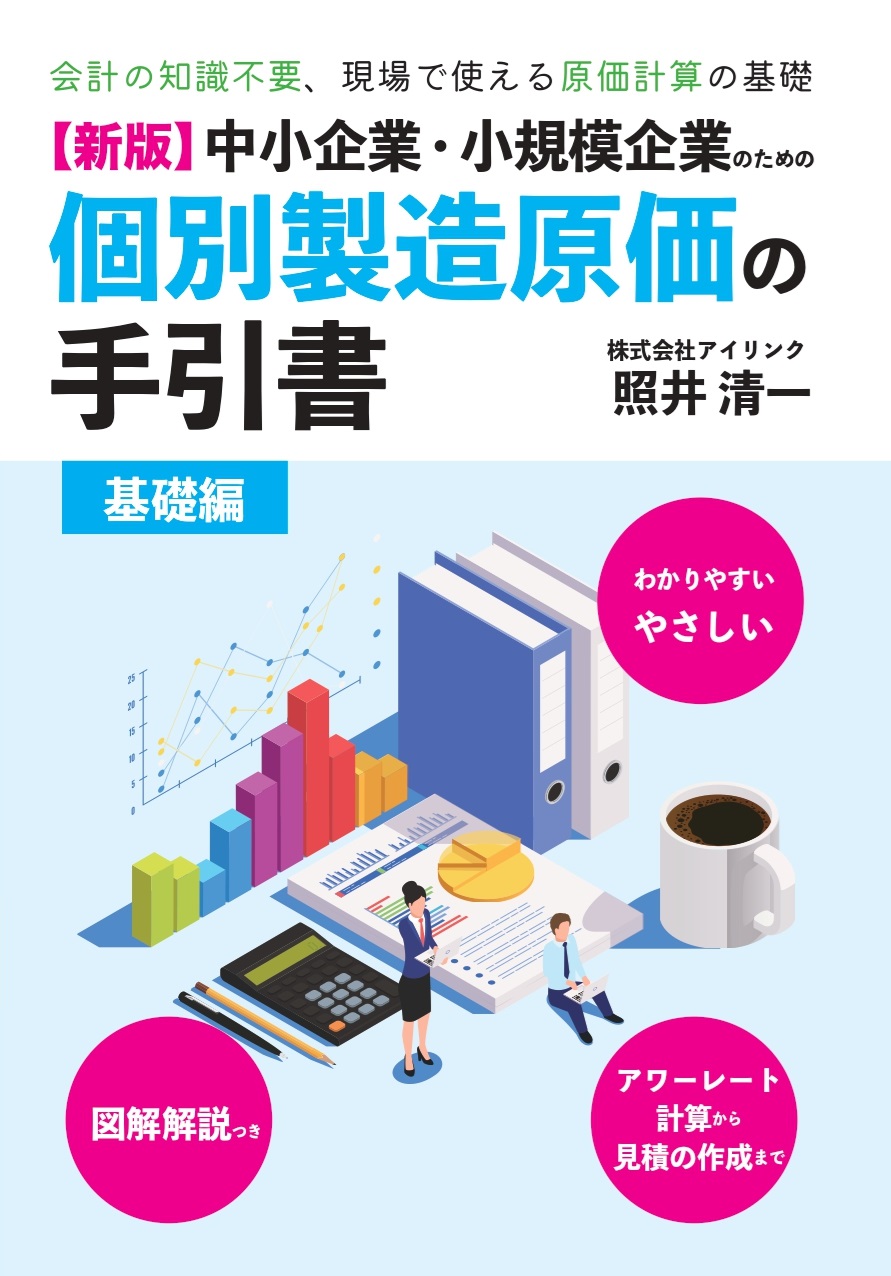
中小企業・小規模企業のための
個別製造原価の手引書 【基礎編】
価格 ¥2,000 + 消費税(¥200)+送料
中小企業・小規模企業のための
個別製造原価の手引書 【実践編】
価格 ¥3,000 + 消費税(¥300)+送料
ご購入及び詳細はこちらをご参照願います。
書籍「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」日刊工業新聞社
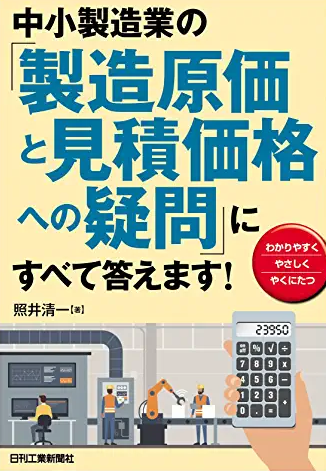
普段疑問に思っている間接費・販管費やアワーレートなど原価と見積について、分かりやすく書きました。会計の知識がなくてもすらすら読める本です。原価管理や経理の方にもお勧めします。
こちら(アマゾン)から購入できます。
簡単、低価格の原価計算システム
数人の会社から使える個別原価計算システム「利益まっくす」
「この製品は、本当はいくらでできているだろうか?」
多くの経営者の疑問です。「利益まっくす」は中小企業が簡単に個別原価を計算できるて価格のシステムです。
設備・現場のアワーレートの違いが容易に計算できます。
間接部門や工場の間接費用も適切に分配されます。
クラウド型でインストール不要、1ライセンスで複数のPCで使えます。
利益まっくすは長年製造業をコンサルティングしてきた当社が製造業の収益改善のために開発したシステムです。
ご関心のある方はこちらからお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。