設備のランニングコストは、使用・維持で発生する変動費です。電気代、消耗品、修繕費、保守契約料などが含まれます。製品生産に比例するものは材料費、設備稼働に比例するものはランニングコストと区別します。電気代は実測か定格から推測し、高額な修理費は定期的なもののみランニングコストに含めます。これらを適切に計算することで、アワーレートを正確に算出できます。
アワーレート(設備)の計算には設備のランニングコストも考慮する必要があります。この設備のランニングコストとはどのようなものでしょうか?
1.アワーレート(設備)の計算
設備が稼働したことによる製造費用(加工費)は以下の式で計算します。
製造費用 = アワーレート(設備) × 製造時間
このアワーレート(設備)は以下の式で計算します。
アワーレート(設備) = 設備の年間費用 ロット数
アワーレート間(人)= 人の年間費用合計+間接製造費用分配 年間操業時間×稼働率
設備の年間費用は
- 設備の購入金額 実際の償却費
- ランニングコスト
この2つです。
例えば
- 実際の償却費 140万円
- ランニングコスト 電気代 18.4万円
- 年間操業時間 2,100時間
- 稼働率 0.8
この場合
アワーレート(設備)= (140+18.4)×10,000 2,100×0.8 = 943 ≒ 940 円/時間
940円/時間でした。
2. 設備のランニングコストとは?
設備のランニングコストとは、設備を使用・維持するために継続して、あるいは時々発生する費用です。減価償却費(あるいは実際の償却費)はすでに過去に支払ったお金で、実際にはお金は出ていきません。しかしランニングコストは設備を使用すればするほど発生します。つまり変動費です。ただし電気代などは、定額部分と従量課金部分があるため、固定費の要素もあります。
ランニングコストの例
ランニングコストは大きく分けると以下の3種類です。
- エネルギー費、消耗品など設備が稼働することで消費するもの
- 修繕費のように突発的な故障で発生する費用
- 保守契約や定期点検のように一定期間の間支出が決まっている費用、故障した時の負担を減らすための保険料もこれに含まれる
エネルギー費、消耗品は、設備によって以下のものがあります。
電気代
設備によっては多額の電気代が発生するものがあります。また設備の大きさによって金額が変わります。
ガス代
加熱のために使用する都市ガス・LPG、熱処理炉では表面処理のためにアンモニア、窒素ガスなど、溶接機はシールドガスとして二酸化炭素、アルゴンなど、レーザー加工機の二酸化炭素
水道代
一部の加工機や射出成形機で使用する冷却水、塗装設備などで使用する水、食品機械の洗浄水
消耗品費
潤滑油、グリス、クーラント、プレス加工油など油脂類、洗浄機で使用する洗浄剤、設備の交換用フィルター、ホースなど交換頻度の高いもの。
ワイヤーカット放電加工機のワイヤー、半自動溶接機の溶接ワイヤーなど設備の稼働によって消耗するもの。
工作機械の刃物、研削盤の砥石のように加工に伴い損耗劣化するもの
修繕費
修理は突発的に発生するため、年間の修繕費は読めないことが多いです。しかし設備が老朽化すれば修理の頻度が高くなります。この修繕費については後で説明します。そうなればこれまでの経験から年間の修理費を見込みアワーレート(設備)組み込みます。毎年多額の修繕費がかかるようであれば、更新した方が原価が低くなることもあります。
保守契約料など
高額な設備の場合、保守点検や保守部品、突発的な修理も含めて保守契約に入る場合があります。保守契約に入れば、1年間でそれ以上の費用がかからず予算も立てやすくなります。これも設備のランニングコストと考えます。
このように設備が消費するものには様々なものがあります。この中で設備毎にランニングコストとして計算するものは、1台あたりの年間消費金額が大きいものに限定します。
具体的な金額例
溶接機のCO2ガス
- 溶接時間(アーク放電している時間) 1時間
- ガス消費量 10l/分
- 7kgボンベ 5,000円
の場合、年間188,500円
計算の詳細
溶接時間(アーク放電している時間) 1時間/日
ガス消費量 10~25l/分 仮に10l/分とする
1時間600l/分
7kgボンベ 5,000円 ガス量3,900l
稼働日245日
年間消費量=245×1×600=147,000l
消費ボンベ=147,000/3,900=37.7本
年間消費金額=5,000×37.7=188,500円
ワイヤーカット放電加工機
ワイヤーの金額
条件
- ワイヤーの消費量400m/時間
- ワイヤーの単価0.4円/m
- 年間加工時間4,000時間
年間消費金額64万円
計算の詳細
年間消費量=4,000×400=1,600,000m
年間消費金額=1,600,000×0.4=640,000円
プレス加工油
プレス加工油の年間金額
条件
- 時間当たりオイル消費量1.2l/時間
- 年間加工時間2,000時間
- オイル単価=750円/l
年間消費金額1,800,000円
計算の詳細
年間消費量=2,000×1.2=2,400l/年
年間消費金額=2,400×750=1,800,000円
3. ランニングコストか、材料費か?
ランニングコストには、ワイヤーカット放電加工機のワイヤー、半自動溶接機の溶接ワイヤー、工作機械の刃物、研削盤の砥石など消耗品があります。
材料費と考える場合
消耗品には、半自動溶接機の溶接ワイヤーのように加工が進むに従い、溶けて溶接部の一部を構成するものもあります。また工作機械の刃物、研削盤の砥石のように加工が進むに従い摩耗するものもあります。このように製品の加工によって使用量が明確になるものは、材料費の一部と考えることもできます。企業によっては、
- プレス加工油を材料費と考え、見積に入れる
- 刃物代を材料副費として、材料費に含めて計上
することもあります。
材料費と考えるかどうかの判断基準
材料費と考えるかどうかの判断基準
- 材料費と考えるかどうかの判断基準製品の生産量に比例して消費 : 材料費
- 設備の稼働時間に比例して消費 : ランニングコスト
また工作機械の刃物代のように、年間での消費金額が大きい場合、工場の消耗品として一律に分配すると、刃物を使用しない設備も刃物代が分配されるため原価が高くなってしまいます。その場合は、刃物代は機械加工現場の固有の消耗品費とするか、設備のランニングコストに入れます。
この「材料費」か「設備費(ランニングコスト)」かの判断の例を以下に示します。
| 項目 | 分類 | 説明 |
| 刃物(ドリル、エンドミルなど) | 材料費またはランニングコスト | 製品ごとに摩耗するため原価と紐づけしやすい |
| ワイヤーカットのワイヤー | 材料費またはランニングコスト | 使用長さが明確な場合は材料費、設備基準で管理する場合はランニングコスト |
| 溶接ワイヤー | 材料費またはランニングコスト | 溶接量に比例して消費されるため、原価にできる |
| プレス油・加工油 | 材料費またはランニングコスト | プレスショット数に比例して消費されるため、原価にできる |
| グリス・潤滑油 | ランニングコスト | 一定時間稼働で徐々に劣化・消費されるため、時間単価で管理が適切 |
材料費とする場合
- 消耗品からその金額をマイナス
- 消耗品費を含む間接費の分配金額が減少
- 個々の見積の材料費にその費用を追加
こうすることで適切な工場の経費を計算し、適切に各現場に分配できます。
4. 電気代の計算
この設備のアワーレートの計算では、設備1台の年間の電気代の値が必要です。
これは簡単にはわかりません。前述のように工場全体で一括請求されるからです。
そこで以下の2つの方法があります。
- 実際の消費電力を測定して、それを元に年間の電気代を推測する
- 設備の定格から消費電力を仮に計算して、それを電気代とする
個々の設備が毎月の消費電力の積算を表示してくれればよいのですが、現実にはそのような設備は多くはありません。
実測
1は実際に運転している設備の一定期間の消費電力を、積算電力計を使って測定する方法です。ただし消費電力は設備の運転状況によって変わり、設備の運転状況は加工する製品によって変わります。そのため測定値はある製品を加工している時の消費電力です。
定格から推測
2はそれも大変な場合、設備の定格から推測する方法です。
これは以下の方法で行います。
例えばA社のマシニングセンタは以下の仕様でした。
3相200V
定格 12.45kVA
消費電力P(kW)は以下の式で計算します。
P = V(電圧) × I(電流) × √3 × 力率 × 負荷率 (kW)
ここで V × I × √3 = 定格 (kVA)
力率 工作機械0.6~0.95、3相モーター0.8~0.85、ヒーター・白熱灯 1.0
負荷率 運転中のモーターにかかる負荷の割合0.5~0.9
計算例
力率と負荷率が以下の値とします。
力率 0.7
負荷率 0.6
この時の消費電力は
P = 定格 × 力率 ×負荷率 = 12.45 × 0.7 × 0.6 = 5.229 kW
ここから年間消費電力は
操業時間 2200時間 稼働率0.8 より
稼働時間 = 操業時間 × 稼働率 = 2200 × 0.8 = 1760時間
年間消費電力(kWh) = 消費電力 × 稼働時間 = 5.229 × 1760 = 9,200 kWh
1kWh当たりの電気代 20円/kWhとすると年間の電気代は
年間電気代 = 1kWh当たり電気代 × 年間消費電力 = 20 × 9,200 = 184,000円
この設備の年間の電気代は184,000円でした。
検算が重要
これは概算なので、最後にこの方法で計算した電気代の検算をします。
具体的には、こうして計算した電気の使用量の多い設備の電気代を合計し、工場の年間の電気代と比較します。 合計が工場の年間の電気代より高過ぎたり、低過ぎたりする場合は、稼働時間や負荷率が違っている可能性があります。その場合、合計が高すぎた場合、低くなるように結果を調整します。
5. 時々発生する高額な修理費をランニングコストと考えるか?
修理は突発的に発生するため、年間の修繕費は読めません。しかし設備が老朽化すれば修理の頻度が高くなります。常に毎年発生する高額な修繕費はランニングコストと考えるべきでしょうか。
設備が老朽化し、常に修繕費が発生するようであれば、年間の維持費用の一部と考えランニングコストに入れます。一方「突発的・異常なトラブル」はアワーレートに含めません。
修理費の例
詳細を以下の表に示します
| 修理の種類 | アワーレートへの扱い | 理由 |
| 定期的な修繕・摩耗部品交換 | 含める(費用を年換算し時間単価に) | 継続的に発生するため |
| 予測困難な突発故障 | 含めない/別途予備費処理 | 原価に含めると過大に見積もる恐れあり |
例えば、老朽化のため毎年何らかの修理が発生し、その金額は3年で平均年間30万円であれば、この30万円をその設備のランニングコストとします。
突発的な故障
しかし突発的な腰用で多額の死有利費が発生した場合、これをアワーレート(設備)の計算に入れるとアワーレート(設備)が高くなってしまいます
例えば、1.アワーレート(設備)の計算で計算した設備に、ある年は300万円の修理費が発生した場合、これをランニングコストとすると
アワーレート(設備)= (140+18.4+300)×10,000 2,100×0.8 = 2,729 ≒ 2,730 円/時間
940 → 2,730 1,790円/時間 増加します。
しかしこの修理はその年だけ発生した突発的な修理であれば、アワーレート(設備)の計算に入れずに940円/時間とした方が適切な原価になります。そこでこの修理費300万円はアワーレート(設備)の計算に入れず、工場経費の修繕費からも300万円をマイナスします。
このように例年は発生しない突発的な費用は、正常な原価と考えず、原価計算では特別損失のように考えます。ただし財務会計上は、修繕費として工場の原価に含まれます。この点は、財務会計と異なる点です。
6. まとめ
本コラムの内容を以下にまとめました
- 設備のアワーレートは、年間の総費用を稼働時間で割って算出します。
- 設備のランニングコストは、電気代や消耗品など、使用によって発生する変動費用です。
- 消耗品は、生産量に比例すれば材料費、稼働時間に比例すればランニングコストと判断します。
- 工場全体の請求から個々の電気代を求めるには、実測するか、設備の定格から推測します。
- 定期的な修繕費はアワーレートに含めますが、突発的な高額修理費は除外します。
経営コラム【製造業の原価計算と見積】【製造業の値上げ交渉】は下記リンクを参照願います。
弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」
原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。
「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」
製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。
書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】
経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。
【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本
【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説
月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。
利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。
セミナー
アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。
オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。
詳細・お申し込みはこちらから

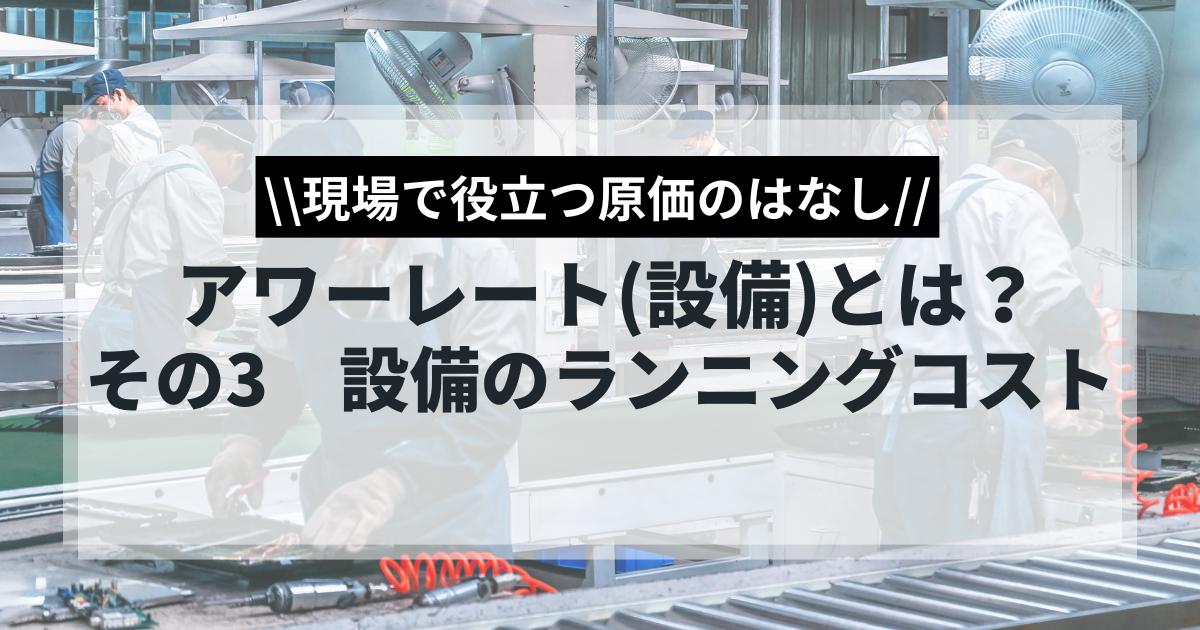

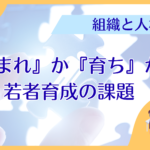
コメント