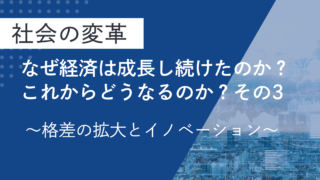 社会の変革
社会の変革 なぜ経済は成長し続けたのか?これからどうなるのか?その3 ~格差の拡大とイノベーション~
【コラムの概要】経済学者ゴードンは、20世紀の経済成長は特別な期間であり、今後は低成長が続くと主張。製造業の自動化やアウトソーシングで中間層の仕事が減少し、格差が拡大していると指摘します。また、IT革命は生産性向上に限界があり、AIが仕事を...
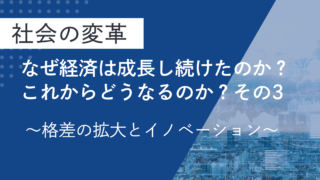 社会の変革
社会の変革  社会の変革
社会の変革  社会の変革
社会の変革 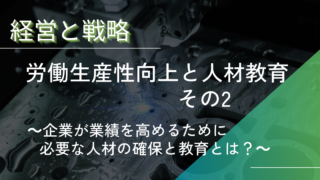 経営と戦略
経営と戦略 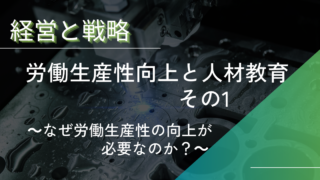 経営と戦略
経営と戦略  社会の変革
社会の変革  社会の変革
社会の変革  社会の変革
社会の変革  社会の変革
社会の変革  社会の変革
社会の変革