取引先からの追加検査要求に対し、コストを正確に把握し、交渉に活用することが重要です。検査員の人件費や設備費、消耗品費など、追加で発生する費用を詳細に積算します。この明確なコストデータを基に、顧客へ追加費用として提示することで、適切な価格転嫁と利益確保が可能になります。あいまいなコスト把握では、企業の利益を圧迫するリスクがあります。
値上げが必要になった原因として、当初より原価が高くなっていることがあります。例えば「検査が追加された」、「当初の見積にない工程が追加された」などです。
検査が追加された場合
例えば、見積した時点では検査費用は入っていませんでした。しかし生産が始まると取引先から「傷があるものは入れないでほしい」と言われました。そのため全数目視検査を追加しました。
この場合、検査費用の分、原価は上がっています。
検査費用の計算
この検査費用は、抜取検査と全数検査で金額が大きく違います。
そこで架空のA社 A1製品に抜取検査と全数検査を追加した場合の原価を計算します。
(A社の詳細は【製造業の値上げ交渉】1. 個々の製品の原価はいくらなのだろうか?を参照願います。)
A1製品
- 製造工程 : NC旋盤
- 製造時間 : 0.075時間
- 製造費用346円
- ロット : 100個
- 材料費 : 330円
- 外注費 : 50円
- 販管費レート : 0.25
検査なしの場合
製造原価=材料費+外注費+製造費用
=330+50+346=726円
販管費=製造原価×販管費レート
=726×0.25=182円
販管費込み原価=製造原価+販管費
=726+182=908円
受注金額が988円の場合、利益は
利益=受注金額-販管費込み原価
=988-908=80円
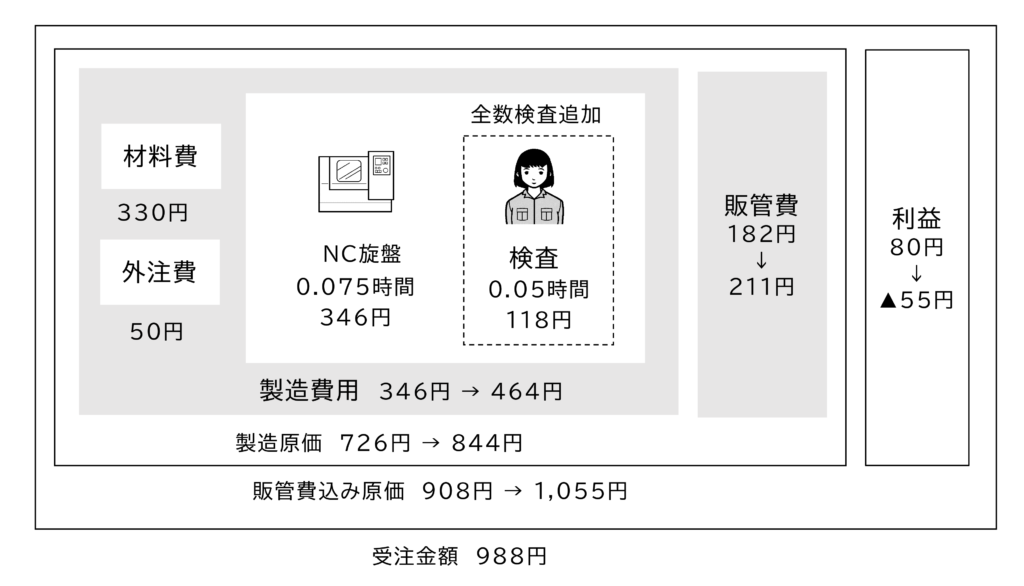
取引先の要求で全数検査を追加し、検査時間は3分(0.05時間)でした。
検査は人が行い設備は使用しないため、アワーレートはアワーレート間(人)のみです。
(アワーレート間(人)は間接製造費用を含んだ人のアワーレートという意味です。詳細は【製造業の値上交渉】2. 我が社の人と設備のアワーレートはいくらなのだろうか?を参照願います。)
検査の現場はパート社員も多く、アワーレート間(人)は他の現場より低く、2,350円/時間でした。
全数検査を追加した場合の原価
全数検査を追加した場合、原価はいくら高くなるのでしょうか。
A1製品の検査費用は
検査費用=アワーレート間(人)×検査時間
=2,350×0.05=118円
製造原価=材料費+外注費+製造費用+検査費用
=330+50+346+118=844円
製造原価が増加したため、販管費も比例して増加します。
販管費=製造原価×販管費レート
=844×0.25=211円
販管費込み原価=製造原価+販管費
=844+211=1,055円
利益=受注金額-製造原価
=988-1,055=▲67円
全数検査を追加したため販管費込み原価は908円から1,055円と147円増えました。
その結果、80円の利益が67円の赤字になりました。そこで増加した147円の値上げを交渉します。
ただしこの147円のうち118円は検査費用ですが、29円は販管費の増加です。この販管費の増加分の値上げは顧客に認めてもらうのは難しいかもしれません。その場合は、検査費用の増加分118円の値上げは認めてもらうようにします。
抜取検査の場合
抜取検査は費用の増加は少なくなります。
A1製品の検査を抜取検査に変更しました。
抜取検査の条件 100個から5個抜取り
(本来はJISの抜取検査に従って抜取り数は決めます。ただし現場では上記のように適当に抜取り数を決める場合も多くあります。)
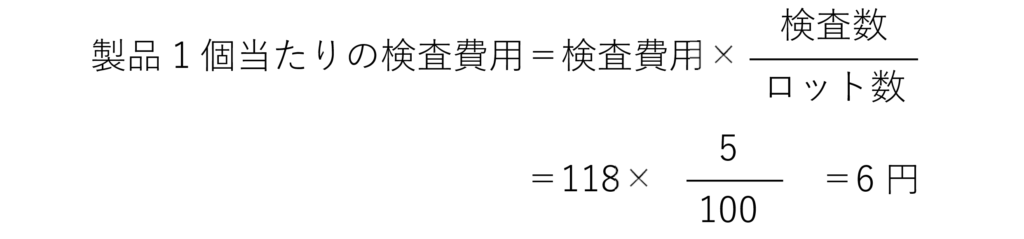
製品1個当たりの検査費用は6円でした。
製造原価=材料費+外注費+製造費用+検査費用
=330+50+346+6=732円
製造原価が増加したため、販管費も比例して増加します。
販管費=製造原価×販管費レート
=732×0.25=183円
販管費込み原価=製造原価+販管費
=732+183=915円
抜取検査を追加したため販管費込み原価は908円から915円と7円増えました。
その結果、80円の利益は73円に減少しました。
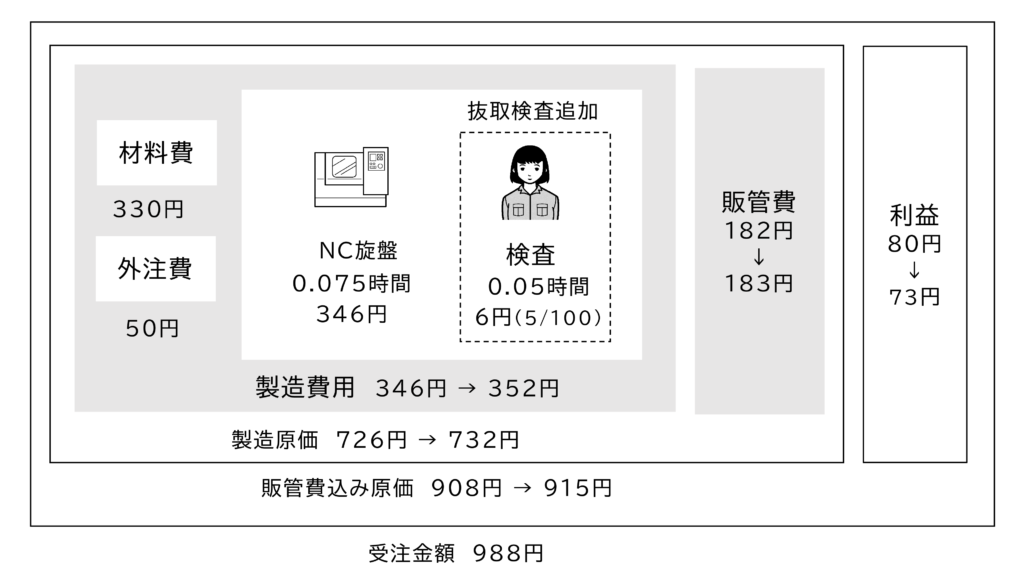
検査を減らすように交渉
全数権を追加した原因は、自社の製造工程で発生した傷のためでした。そのため価格を118円も上げてもらうのは容易ではありません。
そこで、検査で傷のある製品を除外するのでなく、製造工程を改良してできる限り傷を減らして全数検査から抜取検査に変えてもらいます。抜取検査であれば値上げしなくても利益は73円あります。
抜取検査は万全ではありません。しかしその傷は118円のコストをかけて完全に除外しなければならない傷でしょうか?それだけコストがかかっていることを取引先に伝えて、抜取検査への移行に理解を求めます。
それでも取引先は全数検査を要求することがあります。
検査にコストはかからないと思っている
理由は検査にコストはかからないと思っているからです。
顧客自身も自社の工場では検査費用を原価に入れていないことがあります。そうなると議論はかみ合いません。
本コラムで計算する原価は、決算書の数字を元に計算した「真実」です。
3分検査すれば実際に118円の費用が発生します。
その一方で、品質を高め良いものをつくるために「やったほうが良いこと」は、検査の他にもあります。時には取引先はそれを要求します。そしてその費用はつくる側(仕入先)が一方的に負担させられます。
そこで顧客が要求することを行えば原価がいくら上がるのかを具体的に金額を示して、「これだけコストが上がりますがそれでもやりますか」と交渉します。やったほうがよいが、コストをかけるまでもないことも案外多いのです。しかし金額を明示しなければ、いつの間にか「やること」になってしまいます。
具体的な金額を示したのに「値段を上げずにやってほしい」という要求は、これは国のガイドラインに抵触します。このガイドラインについては【製造業の値上げ交渉】19. 下請法や国のガイドラインを値上げ交渉に活かす方法を参照願います。
少なくとも検査費用を社内見積には入れる
一方、社内も検査にコストはかからないと思っていることがあります。それでは取引先から全数検査を要求されても問題だと思いません。
しかし検査を行えば費用は発生します。そこで、まず社内の原価計算に検査費用を入れます。見積にも検査費用を入れます。そうすれば「検査も原価」という意識が生まれます。原価がかかっていれば、現場は短時間に検査をするように努力します。
検査は慌てるとミスが起きるため、カイゼン活動の対象外になっている工場もあります。しかし検査も原価なのです。しかも検査は人が行うため、設備よりもアワーレート(人)が高いことが多く、原価の中で大きな割合を占めることもあります。
取引先と建設的な議論を
見積に検査費用を明記すれば、取引先もつくる側も検査費用を意識します。その上で「どうすれば検査費用を少なくできるか」お互い建設的な議論ができることが望ましいです。
検査以外にも運賃や梱包費用の上昇でどれだけ金額は変わるのでしょうか?
これについては【製造業の値上げ交渉9. 運賃が上昇すれば、いくら高くなるのだろうか?を参照願います。
経営コラム【製造業の値上げ交渉】【製造業の原価計算と見積】【現場で役立つ原価のはなし】の過去記事は、下記リンクからご参照いただけます。
弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」
原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。
「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」
製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。
書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】
経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。
【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本
【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説
セミナー
アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。
オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。
詳細・お申し込みはこちらから
月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。
利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。
経営コラム ものづくりの未来と経営
経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。
以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)


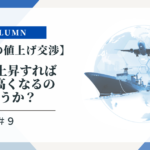

コメント