企業不祥事と組織の問題 その3で日野自動車の排ガス・燃費不正問題、その4で三菱自動車の燃費不正問題を取り上げました。これらに共通するのは不正以外に方法がないところまで担当者を追い込んだ組織と管理者の問題でした。第三者委員会の報告書には従業員アンケートの結果、そこには無理な目標やできないとは言えない企業風土がありました。内向き組織の組織や現場を顧みないリーダーがどんな結果を招くのか、過去には挑戦戦争のマッカーサー元帥もそうでした。
企業不祥事にについて、以下のコラムで取り上げました。
コンプライアンスと内部統制について、「企業不祥事と組織の問題 その1 ~コンプライアンスと内部統制~」
技術者に求められる倫理観と組織の問題について「企業不祥事と組織の問題 その2~工学倫理と問題を起こす組織~」
日野自動車で起きた排気ガス・燃費不正問題について第三者委員会の調査報告書から、「企業不祥事と組織の問題 その3 ~日野自動車の排気ガス、燃費不正~」
三菱自動車の燃費不正問題について、第三者委員会の調査報告書から企業不祥事と組織の問題 その4 ~三菱自動車の燃費不正~
スバル・日産の完成車検査不正について、第三者委員会の調査報告書から企業不祥事と組織の問題 その5 ~スバル・日産の完成検査不正~
組織の問題について、日野自動車、三菱自動車の不正問題の第三者委員会の報告書では従業員アンケートの結果を掲載しています。社員が自社をどのように見ていたのでしょうか。
リーダーの問題について取り上げました。
社員は組織をどう見ていたのか
日野自動車の従業員アンケートの結果
日野自動車特別調査委員会は従業員9,232名にアンケートを行い、2,084通(22.6%)の回答を得ました。その中のいくつか抜粋します。
- そもそも遅延している開発計画をさらに短縮させ、NOと言わせない開発プロセス
- 計画段階で課題が曖昧なまま工数を検討させ、実際に課題が出てきても追加変更が発生しても元の日程のまま作業に突っ込む
- 開発・評価が十分な時間がなく、うまくいく前提の日程しか組まれていない
- 様々な国に向けて多くのモデルを開発、国ごとに法規制が異なるため開発リソースが不十分
- 法規に適合する性能があるか、認定試験に十分な設備があるか、十分に検討せず、実車試験を開始してから問題が表面化
- 現在の開発リソースではやりきれない製品ラインナップ
- 万年赤字の製品や地域があるのに進出したことが評価され、天体は「進出を決めた上司の顔に泥を塗り、失敗を認めることになる」ため良しとしない
- 仕切り会議フェーズは移行管理項目100%が移行条件で問題が残ったままでは次のフェーズに移行できないはずが、「条件付き移行可」で進めていた
- マネージャーの能力・知識や自分の仕事をマネジメントできてなくても、上のいうことに素直に従うイエスマンが昇格する
- 「問題解決ができない」「日程を守れない」と報告すると「こいつは能力が低い」と評価されてしまう
- 「できない」と報告しても「どうしてできないんだ説明しろ」と言われてしまい、できないことを説明するのが難しく、できない状況を説明する時間がもったいないので業務を優先してしまう
- 達成不可能な目標を精神論で乗り越えた社員が評価される風土がある
- 見かけ上の成果を上げた社員が評価され、その後同様の影響力を行使するという悪循環
- 組織改革をが続き組織の分裂や統合により従来の組織で対応していた役割が引き継がれずに三遊間が生まれる
- 自分たちのやってきたことは正しいと思い込んでいる人たちにより変革が進まない
- 「今まで問題なかったのになぜ変えなきゃいけないんだ」「俺の言うことを否定するのか」など恫喝とも取れる態度で接する傾向がある
- 経営層が決定を下すまでの情報収集や資料作成に必要以上に時間がかかる
- 権限移譲が進んでおらずなんでも上の方にまでもっていく必要があるため、社長や役員へ報告・相談を行う、そこで何か一言コメントしなければならないと思った上の人がコメントするとそれが宿題になって雪だるま式に仕事が増える
- 問題が発覚して日程に間に合わなければ担当者が開発状況を管理する部署の前で説明させられ責任を取らせる「お立ち台」
アンケートの結果から、困難な目標や日程に対し、管理者は担当者をサポートするどころか、叱責して追い詰めるばかりで、具体的な解決策を提示になかった様子が伺えます。
三菱自動車の社内アンケートと社員へのヒアリング結果
特別調査委員会は2026年三菱自動車の開発本部及びMAEの社員4500人にアンケートを行い、849通の回答を得ました。主な意見を以下に示します。
- プロジェクトの途中で営業部門からの意見で自動車のコンセプトや使用、場合によってはプラットフォームやエンジンの使用まで変更になることがある
- MMCにおけるとりまとめは一般的なマネジメントではなく形式的な集約作業に過ぎず、取りまとめをしている者は、案件の実務を担当者に丸投げしている、また責任も担当者に押し付けている
- エキスパートや担当部長が、開発目標の達成が困難である旨の相談に対して聞く耳を持たず「とにかく目標を達成しろ。やり方はお前らが考えろ」としか言わないため、相談しようという気になれない
- 部署の上の人は部門の上の人に対してイエスマンの状態、下の者は無理だと思っていても上の人が更に上に「やれます」と言っているため、上に行っても無理なことが分かっているから言いに行けるところがない
- 開発の現場を本社経営陣が把握していないと感じ、今まで開発現場の意見が上がっているはずだが、改善される様子はなく、開発現場では諦めに似た空気も出ている
- 経営幹部が見て回っているところがなく、少しでも時間をかけて自分の目で確かめる行動をしてほしい
- 過去の不祥事の際にそれに対する総括が社員に示されていない

図9 正しい情報が上がってこない
2011年に従業員に対して行ったコンプライアンスアンケートの結果、コンプライアンス問題としてアンケートに記載されていたことには以下のものがありました。
- 競合他社がやっているとはいえ、燃費を上げるために実用上かけ離れたことをやること
- 無謀な超短期日程、少ない人員で開発した自動車は極めて品質が悪い
- リコール問題を起こす前と状況が似ており、再びリコール問題が起きるのではと危惧している
- 虚偽方向などいまだに存在する
- 納期を守るための偽造データの作成
また2009年から2015年にかけて行われた性能実験及び認証部における技術倫理問題検討会では以下の指摘がありました
- 根本にある考え方=減点主義、事なかれ主義(自部門の責任ではないことを示したい)、コスト優先になっている(損費を減らしたい意識)
- 悪い話は早く報告する姿勢を求められながらも、実際に報告すると怒られる→この体質改善が必要。不具合報告をした人が損をする体質を改善するべき
- 技術的裏付け(試験結果も含む)なく妄想レベルでハードが決定される
- 開発キックオフの時の技術構想が不十分(このシステム、開発期間で各規制、目標を達成できるか)
- 開発キックオフ時の技術構想案についてできそうにないと感じても、できないことの証明がうまくできない
- 検討のための時間を確保するのが難しい(別機種を開発している)ことも一因
技術開発の現場ではうまくいかないことや失敗は常に起きます。それを一人で解決するのは限りがあります。
多くの企業はこうした困難に対し、様々な部署や人が協力して克服しました。それがお互いに背を向けて自分の問題だけ見ていれば、組織の力が発揮できません。
過去にリコール隠しというコンプライアンス違反があった同社は、コンプライアンスに対するアンケートや企業倫理問題検討会を実施してきましたが。そこでは今回の不祥事の原因となるような問題も報告されていました。しかしこうした組織や管理者の問題は改善されませんでした。
組織とリーダーの問題
これまで見てきた日野自動車、三菱自動車、日産、スバルで起きた問題は、それぞれ企業固有の問題でしょうか。これらの問題は、経営陣や幹部社員が現場や社員を置き去りにして、業績や生産性を追求した結果、必然的に発生したものではないでしょうか。
そうならばこうした不祥事は、どこの企業でも起きるのではないでしょうか。
十分な検討や技術的な裏付けの元、目標が設定されていたか?
日野自動車、三菱自動車では、経営陣が技術的な知見に照らして実現可能性を再考することなく、担当部門や担当者に目標実現のプレッシャーを強くかけました。その結果、担当者を不正しか方法がない状況に追い込まれました。その背景に実力以上の製品ラインナップや開発期間の短縮がありました。そしてこうしたことが常態化したため、現場は疲弊し声を上げることもなくなっていました。
現場の疲弊は経営者にまで伝わっていたか?
完成車検査制度や惰行法による排ガス測定は、当時の自社のリソースから見れば無理な状況でした。にもかかわらず現場だけで解決しようとして、法規から逸脱してしまいました。スバルや日産の不正は、わずか数十人の完成検査員の不足が原因です。もし不正の影響の大きさ、発覚した場合の損失金額を考えれば、少なくとも経営者ならばいくらでも手を打つことができた問題でした。しかし経営者は問題を適切に把握できていませんでした。そして問題は現場から経営者に伝わらず、発覚して初めて経営者は知りました。その原因に以下の2つの要素が考えられます。
内向き組織と現場を見ないリーダー
内向き組織
日本社会はムラ社会といわれます。そして企業もムラ社会であると同時に、企業内部の組織もムラ社会を形成します。ムラの中では、ムラ(組織)を守ることが優先されます。時には会社全体の利益よりもムラが優先されます。例えばスバルでは老朽化した設備の更新は経営陣に訴えられず、現場が工夫して何とかしようとします。その結果が不適切な検査でした。
三菱自動車の性能実験部は、会社の中で、自分たちのムラの立場でもできないと言えませんでした。その結果楽観的な回答を経営陣にしていました。
こうした価値観の中に、こうした結果からもたらされる“性能の出ていない車”を買う顧客のことはあったのでしょうか。
現場・現実を見ないリーダー
製品全体を取りまとめるプロジェクト責任者が「担当した製品がどのようなもので、試験評価の結果がどうなっているのか」関心を持つのは当然です。評価は担当部署が行うとしても、評価状況を実際に見て、評価の担当者から直接話を聞き、情報を得るのはリーダーとして必要なことです。
それは職制を通じて上がってくる情報には様々なフィルターがかかっているからです。自分の目で見たことと、報告される情報を突き合わせて、初めて適切な判断ができるのではないでしょうか。
頑張ればできることと、頑張ってもできないことの区別
「できない」という報告をリーダーはどう理解したのでしょうか。燃費や排ガス性能にはトレードオフの要素があります。それでもチューニングによって改善できる余地はあるかもしれません。しかしそれは頑張ってできるのか、その判断は容易ではありません。それでも物理的な制約を超えて、「できない」ことが「できる」ようになりません。どれだけ頑張っても、船は空を飛べないし、飛行機は水に潜ることはできないのです。燃費に不利なスクエアストロークのエンジンで、他社のロングストロークのエンジンと同等の燃費性能を出すの、現実には可能だったのでしょうか。不可能を強要したのであれば、担当者に残された手段は不正しかありません。
戦場を一度しか訪れなかった将軍
官僚組織ではリーダーには部下から情報が自然と集まってきます。それに対し個々に指示を下せばリーダーの仕事はできます。しかし部下の報告だけで行う判断と、自ら現場を訪れ、現場の空気感に触れた判断は異なります。
北朝鮮の金日成が突如38度線を越えて始まった朝鮮戦争で国連軍を指揮したのはGHQのダグラス・マッカーサーでした。彼はずっと東京のGHQ本部で指揮を執り、朝鮮半島の戦場を訪れたのは1度だけ、しかも日帰りでした。彼には、夏服しか支給されず、氷点下の冬の朝鮮半島で戦うアメリカ兵のつらさをわかっていたのでしょうか。
朝鮮戦争では、突如北朝鮮軍の侵攻を受けた韓国軍は総崩れとなり国連軍(実態はアメリカ軍)も釜山にまで追い詰められました。しかしその後の仁川上陸作戦をきっかけに国連軍は反攻に転じ、北進を続けた国連軍はトルーマン大統領の意に反して中国国境付近まで進軍しました。この時、中国の周恩来首相はアメリカに「これ以上の進軍は許さない」と警告しました。しかし側近はマッカーサーの機嫌を損なうことを恐れ都合のいい情報しか報告せず、マッカーサーも中国の介入はないという思い込みがありました。そのため中国軍の行動を知らせる情報が入っても、よもや中国が参戦するとは思いませんでした。
11月1日彭徳懐が率いる30万人の中国軍が突如攻撃を開始、国連軍は多大な損害を出しました。国連軍は38度線まで後退し、マッカーサーはトルーマン大統領に原爆の使用許可を求めるほどうろたえました。
コールセンターの異常さを見た社長
花王のエコナクッキングオイル(以降エコナ)は特定保健用食品の許可を得たこともあり、年間売上が200億円、他社にはない強力な商品でした。グリシドールという物質には発がん性がありますが、エコナに含まれるグリシドール脂肪酸エステルは全く別の物質です。そしてグリシドール脂肪酸エステルがグリシドールになるという科学的な根拠はありません。
ところが2009年消費者団体が「エコナ=発がん性」と主張したことで、エコナの発売停止とトクホの取り消しを求める運動を展開しました。マスコミもこれを大きく取り上げました。花王はエコナの販売を自粛し、安全性の説明を続けましたが、報道は更に過熱しました。
花王の尾崎社長は、自らコールセンターに行って、電話が鳴りっぱなしの現場を見ました。「大量の電話がきて、その状態が続くのは異常なことだと。電話の中身はさまざまだったが、社員がかかりきりになるような事態は経営者として続けさせるわけにはいかない。いったん撤退して事を収め、そのうえで再出発しようと決めた。
…社長として安全かどうかという議論よりも、まずこの流れを止めないと会社の存続にもかかわると判断した。」
もし尾崎社長がコールセンターを訪れていなかったら、判断はどうなったのでしょうか。
参考文献
「調査報告書」2022年8月1日日野自動車(株)特別調査委員会
三菱自動車「燃費不正問題に関する調査報告書」 2016年8月1日特別調査委員会
日産自動車「調査報告書」2017年11月17日西村あさひ法律事務所
スバル「完成車検査の実態に関する調査報告書」2017年12月19日長島・大野・常松法律事務所
「それでも企業不祥事が起こる理由」國廣正 著 日本経済新聞社
「ザ・コールデスト・ウィンター」デビッド・ハルバースタム 著 文藝春秋
この記事を書いた人
経営コラム ものづくりの未来と経営
経営コラム「ものづくりの未来と経営」は、技術革新や経営、社会の変革などのテーマを掘り下げ、ニュースからは見えない本質と変化を深堀したコラムです。「未来戦略ワークショップ」のテキストから作成しています。過去のコラムについてはこちらをご参照ください。
以下から登録いただくと経営コラムの更新のメルマガをお送りします。(ご登録いただいたメールアドレスはメルマガ以外には使用しません。)
弊社の書籍

「中小製造業の『原価計算と値上げ交渉への疑問』にすべて答えます!」
原価計算の基礎から、原材料、人件費の上昇の値上げ計算、値上げ交渉についてわかりやすく解説しました。
「中小製造業の『製造原価と見積価格への疑問』にすべて答えます!」
製品別の原価計算や見積金額など製造業の経営者や管理者が感じる「現場のお金」の疑問についてわかりやすく解説した本です。
書籍「中小企業・小規模企業のための個別製造原価の手引書」【基礎編】【実践編】
経営コラム「原価計算と見積の基礎」を書籍化、中小企業が自ら原価を計算する時の手引書として分かりやすく解説しました。
【基礎編】アワーレートや間接費、販管費の計算など原価計算の基本
【実践編】具体的なモデルでロットの違い、多台持ちなど実務で起きる原価の違いや損失を解説
月額5,000円で使える原価計算システム「利益まっくす」

中小企業が簡単に使える低価格の原価計算システムです。
利益まっくすの詳細は以下からお願いします。詳しい資料を無料でお送りします。
セミナー
アワーレートの計算から人と設備の費用、間接費など原価計算の基本を変わりやすく学ぶセミナーです。人件費・電気代が上昇した場合の値上げ金額もわかります。
オフライン(リアル)またはオンラインで行っています。
詳細・お申し込みはこちらから

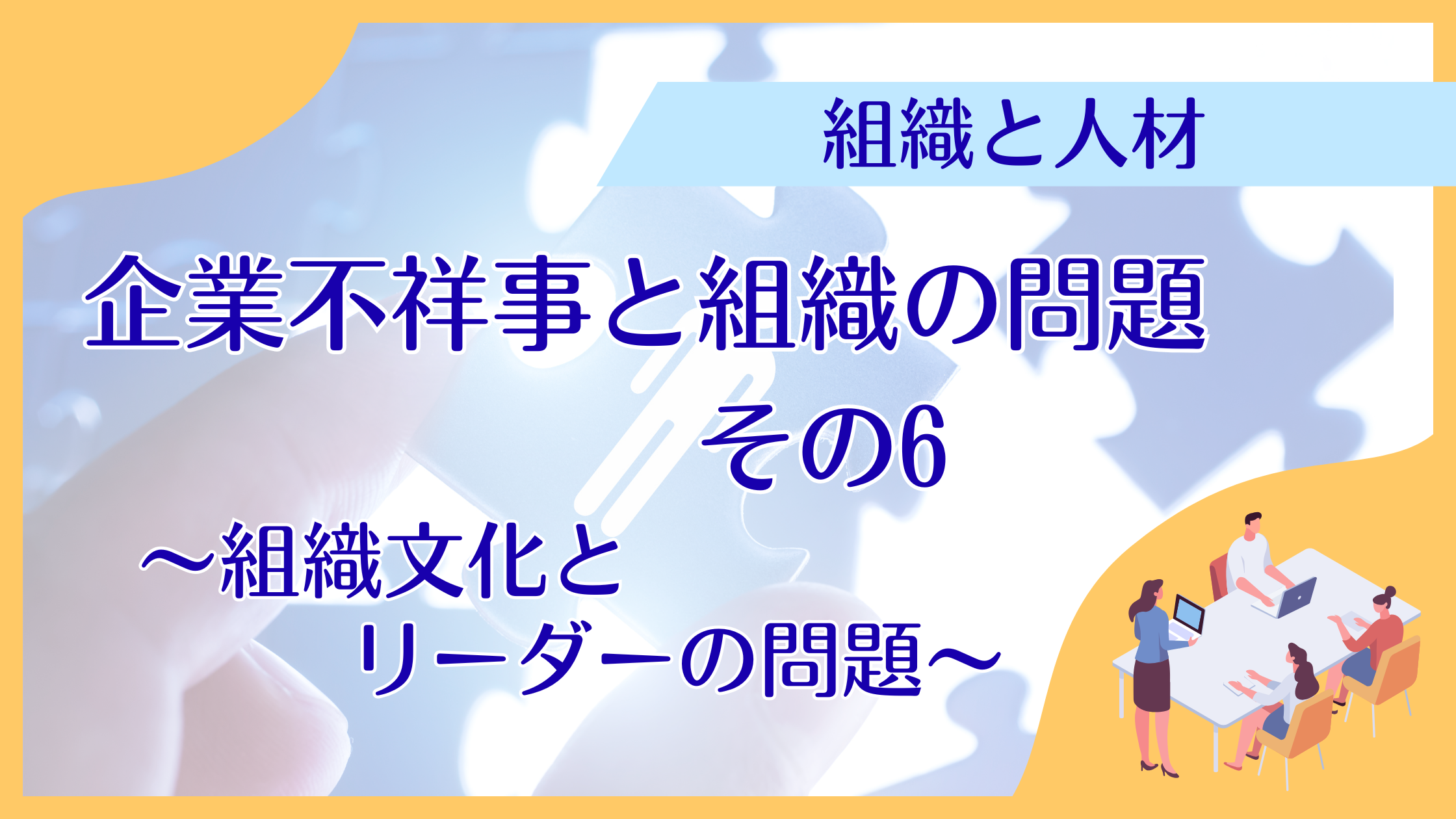


コメント